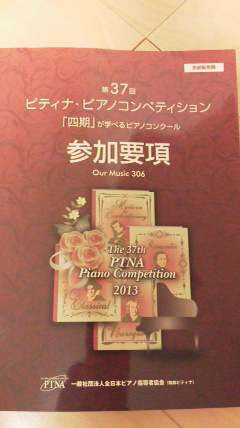3、4歳の生徒さんの中には、
「先生と同じように弾いてみてね。」と見本をみせても、
自分の好きなふうに弾きたい、
とマネをしたがらない場合があります。
そんな生徒さんに、
こちらの要望に答えてもらう方法があると知り、
半信半疑で試してみたら効果的面でしたのでご紹介します。
「先生と同じように弾いてみてね。
その後、向こうにある紙に好きな色でマルを書いて、
書けたらこのお部屋のドアを閉めてきてね!」
ほとんどの生徒さんがおもしろがって、
「次は何の音?もう一回やりたい!」
と取っついてくれました。
不思議なものです。
この技、ご家庭でも応用してみてくださいね!
主に六地蔵、石田、醍醐、御蔵山、木幡、日野、春日野地区より、多くの方にお越しいただいています。 無料体験レッスン随時受付中です。 土日祝もレッスン可能です。 オンラインレッスン、出張レッスンも実施しております。 こどもレッスン、大人レッスン、シニアレッスンお気軽にお問合せください→ https://pianist-sakura.blogspot.com/p/blog-page_7.html
2013年3月14日木曜日
2013年3月11日月曜日
楽譜、お月謝袋、シール
週末、リニューアルしたJEUGIA三条本店http://sanjo.jeugia.co.jp/に行ってきました。
生徒さんたちにぜひ弾いてもらいたい曲の入った楽譜や、お月謝袋、出席カードに貼るシールなど仕入れてきました。
楽譜は欲しいものがたくさんありすぎて、厳選してひとまずこれだけ購入。
お月謝袋は新柄が発売されていました。
シールは男の子が喜びそうなもの、女の子のもの、両方選びました。
生徒さんたちが楽しくレッスンに通えるように、今後もいろいろ仕入れます。
生徒さんたちにぜひ弾いてもらいたい曲の入った楽譜や、お月謝袋、出席カードに貼るシールなど仕入れてきました。
楽譜は欲しいものがたくさんありすぎて、厳選してひとまずこれだけ購入。
お月謝袋は新柄が発売されていました。
シールは男の子が喜びそうなもの、女の子のもの、両方選びました。
生徒さんたちが楽しくレッスンに通えるように、今後もいろいろ仕入れます。
2013年3月8日金曜日
映画のサントラ
こんばんは。
さて、本日はこんなご質問を皆様に。
「お気に入りの映画はありますか?」
午前中に次男と友人のお宅に遊びに行ったら、上映中の『レ・ミゼラブル』のサントラのピアノ楽譜がありました。
電子ピアノもあったので、楽譜見ながらひととおり弾かせてもらいました。
とっても心に沁みる曲ばかりで、弾きながら何だか切ない気持ちになってしまいました。
すでにご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、本当に素敵なものばかりなんです。
ぜひ映画館にも足を運んでみたくなりました。
映画のサントラのピアノ楽譜は、初心者用にアレンジされているものも出回っていて、誰でも気軽に弾いてみることができると思います。
お気に入りの映画があったら、サントラをぜひ弾いてみてはいかがでしょうか。
ストーリーを思い返しながら演奏すると、その作品への思い入れがさらに増すと思いますよ。
さて、本日はこんなご質問を皆様に。
「お気に入りの映画はありますか?」
午前中に次男と友人のお宅に遊びに行ったら、上映中の『レ・ミゼラブル』のサントラのピアノ楽譜がありました。
電子ピアノもあったので、楽譜見ながらひととおり弾かせてもらいました。
とっても心に沁みる曲ばかりで、弾きながら何だか切ない気持ちになってしまいました。
すでにご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、本当に素敵なものばかりなんです。
ぜひ映画館にも足を運んでみたくなりました。
映画のサントラのピアノ楽譜は、初心者用にアレンジされているものも出回っていて、誰でも気軽に弾いてみることができると思います。
お気に入りの映画があったら、サントラをぜひ弾いてみてはいかがでしょうか。
ストーリーを思い返しながら演奏すると、その作品への思い入れがさらに増すと思いますよ。
2013年3月7日木曜日
ピティナ・ピアノコンペティション説明会
こんばんは。
だいぶ春めいた陽気になってきましたね。
そんな中、ピティナ・ピアノコンペティションの課題曲説明会に行ってきました。
この参加要項の表紙にも書かれているとおり、四期が学べるピアノコンクールです。
クラシック音楽は主に時代ごとに四期に分類されています。
1.バロック時代・・・(17世紀初頭から18世紀半ば)
この時代にはまだピアノは存在せず、チェンバロやクラビコード、オルガンなどが使われていました。この時代の作品は主に教会で演奏されることが多かったようです。
代表的な作曲家はバッハやヘンデルなどがあげられます。
2.古典派の時代・・・(1730年代から1810年代)
ピアノフォルテ(現在のピアノ)が発明され、表現できる音の幅(バロックの楽器では出せなかった弱い音と強い音)がだいぶ広がりました。
モーツァルトやベートーベン、ハイドンなどがこの時代の作曲家です。
3.ロマン派の時代・・・(19世紀)
古典派で重視されていた音楽の形式にとらわれず、ショパンの作品のような自由な形式の音楽が作曲されました。またドビュッシーなどに代表されるフランス音楽では絵画的な要素を含んだ楽曲が作られるようになりました。
4.近・現代・・・(1950年以降)
無調の音楽が書かれるようになりました。滝廉太郎や山田耕作などは日本を代表するこの時代の作曲家です。
バスティンもこの時代にあたります。
(ものすごく大雑把にご説明しました。足りない点が多いので詳しく知りたい方はご連絡くださいね。)
これら全ての時代の中から課題曲が選曲されていて、参加者はさらにその中から自分に合った曲を選ぶということになっています。
説明会では審査員も務められている石黒加須美先生先生・美有先生が、課題曲一曲一曲のポイントを話してくださったほか、予選通過に不可欠な要素や選曲の仕方、当日までの練習計画の立て方、生徒さんや保護者の方々への声かけのしかたなど、わかりやすくお話してくださいました。
今年のコンペに生徒さんが参加するかどうかは別としても、日々指導をするうえで役に立つことをたくさん教わってきたのでさっそくレッスンに生かしていきたいです。
ピティナピアノコンペティション、ご興味お持ちの方はぜひご連絡くださいね。
だいぶ春めいた陽気になってきましたね。
そんな中、ピティナ・ピアノコンペティションの課題曲説明会に行ってきました。
この参加要項の表紙にも書かれているとおり、四期が学べるピアノコンクールです。
クラシック音楽は主に時代ごとに四期に分類されています。
1.バロック時代・・・(17世紀初頭から18世紀半ば)
この時代にはまだピアノは存在せず、チェンバロやクラビコード、オルガンなどが使われていました。この時代の作品は主に教会で演奏されることが多かったようです。
代表的な作曲家はバッハやヘンデルなどがあげられます。
2.古典派の時代・・・(1730年代から1810年代)
ピアノフォルテ(現在のピアノ)が発明され、表現できる音の幅(バロックの楽器では出せなかった弱い音と強い音)がだいぶ広がりました。
モーツァルトやベートーベン、ハイドンなどがこの時代の作曲家です。
3.ロマン派の時代・・・(19世紀)
古典派で重視されていた音楽の形式にとらわれず、ショパンの作品のような自由な形式の音楽が作曲されました。またドビュッシーなどに代表されるフランス音楽では絵画的な要素を含んだ楽曲が作られるようになりました。
4.近・現代・・・(1950年以降)
無調の音楽が書かれるようになりました。滝廉太郎や山田耕作などは日本を代表するこの時代の作曲家です。
バスティンもこの時代にあたります。
(ものすごく大雑把にご説明しました。足りない点が多いので詳しく知りたい方はご連絡くださいね。)
これら全ての時代の中から課題曲が選曲されていて、参加者はさらにその中から自分に合った曲を選ぶということになっています。
説明会では審査員も務められている石黒加須美先生先生・美有先生が、課題曲一曲一曲のポイントを話してくださったほか、予選通過に不可欠な要素や選曲の仕方、当日までの練習計画の立て方、生徒さんや保護者の方々への声かけのしかたなど、わかりやすくお話してくださいました。
今年のコンペに生徒さんが参加するかどうかは別としても、日々指導をするうえで役に立つことをたくさん教わってきたのでさっそくレッスンに生かしていきたいです。
ピティナピアノコンペティション、ご興味お持ちの方はぜひご連絡くださいね。
2013年3月5日火曜日
ショパン社『ブルグミュラー25の練習曲』
お気に入りの楽譜、ショパン社の『ブルグミュラー25の練習曲』が廃盤となってしまいました。
ブルグミュラーは他の出版社のものもありますが、このショパン社のものには和音記号(Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ)やコードネーム(C・Am・G7 など)が書かれていて、バスティン教材で和音記号や英語音名も教えている私にとっては、とてもありがたかったのですが。
ブルグミュラーは他の出版社のものもありますが、このショパン社のものには和音記号(Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ)やコードネーム(C・Am・G7 など)が書かれていて、バスティン教材で和音記号や英語音名も教えている私にとっては、とてもありがたかったのですが。
さらに、これには『ブルグミュラーの再発見』という指導書も別にあり、こちらも大変役に立っています。(こちらも廃盤だそうで、そうなる前に購入しておいてよかったです)
ということで、生徒さんに購入してもらうブルグミュラー、どこの出版社のものにしよう。。。
いくつか見比べて決めたいと思います。
2013年3月3日日曜日
新年度ご案内用紙と出席カード完成
今週末、新年度の『ピアノ教室のご案内』の用紙と出席カードを完成させました。
4月からは個人レッスン年44回、グループレッスン年22回のお月謝制ということに決めさせていただきました。
昨日から順次お配りしています。
レッスン回数が把握しやすいよう、出席カードも作りました。
レッスンのたびに好きなシールを選んで貼ってもらおうと思っています。
ピアノ指導をさせていただくにあたって、指導の内容を充実させることはもちろん重要ですが、それだけではなくお教室の運営面にも目を向け、皆様が気持ちよくお子様を通わせることができるようなお教室作りを目指しています。
(文章のみのブログにしよう思っていたのですが「写真も載せてみたら?」とご意見いただきましたので載せてみました。いかがでしょうか。。)
4月からは個人レッスン年44回、グループレッスン年22回のお月謝制ということに決めさせていただきました。
昨日から順次お配りしています。
レッスン回数が把握しやすいよう、出席カードも作りました。
レッスンのたびに好きなシールを選んで貼ってもらおうと思っています。
ピアノ指導をさせていただくにあたって、指導の内容を充実させることはもちろん重要ですが、それだけではなくお教室の運営面にも目を向け、皆様が気持ちよくお子様を通わせることができるようなお教室作りを目指しています。
(文章のみのブログにしよう思っていたのですが「写真も載せてみたら?」とご意見いただきましたので載せてみました。いかがでしょうか。。)
2013年3月2日土曜日
ヤル気を引き出す
『生徒さんたちのヤル気を引き出すこと』
これは指導者にとってとても重要な任務だと思っています。
先日の発表会を終え、保護者の方から
「発表会が終わったらたくさん練習するようになった」
「夢中になってピアノを弾いている」
「おともだちが弾いていた曲を次は弾いてみたいと言っている」
などなど、たくさんの嬉しいご報告をいただきました。
やはり、普段のレッスンとは別の勉強の場を持つことは大切なのですね。
新たな発見が一人一人にあったのだと思います。
ヤル気を引き出すひとつのきっかけになるようなイベントの企画や参加の呼びかけなど積極的に行なっていきたいです。
これは指導者にとってとても重要な任務だと思っています。
先日の発表会を終え、保護者の方から
「発表会が終わったらたくさん練習するようになった」
「夢中になってピアノを弾いている」
「おともだちが弾いていた曲を次は弾いてみたいと言っている」
などなど、たくさんの嬉しいご報告をいただきました。
やはり、普段のレッスンとは別の勉強の場を持つことは大切なのですね。
新たな発見が一人一人にあったのだと思います。
ヤル気を引き出すひとつのきっかけになるようなイベントの企画や参加の呼びかけなど積極的に行なっていきたいです。
登録:
投稿 (Atom)